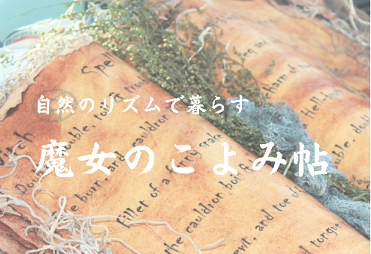【二十四節氣】大暑
暦便覧
暑氣いたりつまりたるゆえんなれば也
太陽黄経120度の時、旧暦六月未の月の中氣。
一年で最も暑く、時折、大雨や雷が鳴り、季節のエネルギーが降り注ぐことで、体調的にも精神的にも影響を受けやすい時期です。

暑中見舞いを送るのは大暑の最後の日までで、
この日以降に送るご挨拶は『残暑見舞い』となります。
大暑 七十二候
初候 桐始結花(きり はじめて はなをむすぶ)
次候 土潤辱署(つち うるおうて むしあつし)
末候 大雨時行(たいう ときどき ふる)
大暑 ならわしと生活

打ち水と桶
埃が立たないように、そして涼をとるために撒く打ち水は、元々神さまの通り道を浄めるもので、家の周りに打ち水をすることはその『場』を浄めるという意味もあります。
また、打ち水の時に使う桶の音にも呪力が込められていると言われます、
桶は古代の鎮魂の祭りの道具として用いられていて、伏せてそれを踏み轟かせるというように使われていたそうです。
これは天岩戸開きの神話の中で天鈿女命が踊り台として使ったという逸話から来るものだと言われます。
ルーナサ Lughnasadh

8月1日に行われるルーナサはケルトの光明神ルーの祝祭で、最初の収穫祭です。
大地の実りを取り入れ、越冬のために蓄えます。
パンやブラックベリーをいただいて、感謝と共に眠りにつく男神へ春に再び大地をよみがえらせるための祈りを捧げます。
ルーナサの祝祭では、特に食べ物を分け合い、そして感謝することが大切であると言われています。
八朔(8月1日)
お世話になった人や頼りにしている人へ贈り物をして「頼み・頼まれる」繋がりを強くするためのならわしです。
旧暦の8月1日はグレゴリオ暦でいうと9月初旬頃となります。
稲が実りを迎える時期でもあり、初めて実った穂を大切な方へ贈る習わしとなったそうです。

頼み→田の実
なので稲穂なのですね♪
土用
大暑に入る前後に迎える夏の土用。
土用の期間は季節の変わり目であり、今の季節と次の季節を調和させて次の季節への準備期間となります。
夏の土用の期間は、成長を一旦おとろえさせて平穏の為に一休みする期間となります。
無理して何かをしようとせずに、本来の自分の軸を定めるよう努めると良い期間です。

土いじりや土を起こす(行動を起こす)ことをせず、
為すがままに任せて過ごすのが良いと言われる土用の期間は
自分を整えることを優先させるときでもあります。
とはいえ、変化や革新のエネルギーが満ちる夏の土用。
土用干しをして湿氣を抜きつつ、自分を整えて確固たる土台を作るのに良き時期です。

ちなみに夏の土用と言えば『土用の丑の日』ですが、
これは、
未の月は五行で火の氣にあたり、
相剋する十二支は丑で水の氣です。
水の氣は黒で表されるため、『丑』の日に『う』のつくものや、黒いものをいただくと良いと言われるようになったとか。

土用の食
土用は方角で言うと中央に対応していることから、人体では「お腹(胃腸)」に対応し、この期間は特に胃腸に疲れや症状が現れやすいとされています。
胃腸にトラブルが出なければ、代謝が上がりやすいためダイエットに最適な季節でもあると言われます。
身体を冷やさず、胃腸に負担の少ない食事やす少量でも栄養価の高いものを取り入れることが良いとされています。
土用の丑の日にいただくとされる『うなぎ』のほか、
消化を助け散血作用や清熱作用のある豆腐もお勧めな食材です。

この時期おススメは、
ハイビスカスとローズヒップを同じ割合でブレンドしたハーブティ。
疲労回復やむくみなどに良いとされるハイビスカスは愛の魔法に用いられるハーブでもあります。
暑さでイライラしがちな時、夏の疲れに。

文字通りめちゃくちゃ暑い日が続いてますが、
できる範囲で無理なく過ごしていきたいですね。
暑さがめちゃくちゃ苦手なので、いつも以上にエコモードで過ごすことにしています。