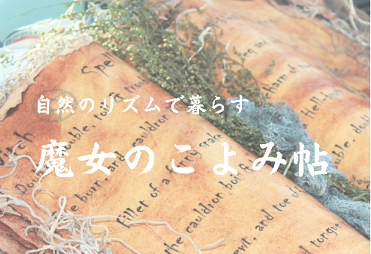清明
暦便覧
万物発して清浄明潔なれば、此芽は何の草としれる也
全てが明るく清らかで生き生きと輝く頃。
春分後15日、太陽黄経15度の時。
清明は『清浄明潔(せいじょうめいけつ)の略であると言われます。
太陽が万物を江良氏、天地全てのものが清く明るく、鮮やかに見える頃。
百花が咲き競い、清らかな空氣の中に輝くこの時期は、自分本来の力を発揮しやすい時期でもあります。
七十二候
初候 玄鳥至(つばめきたる)
次候 鴻雁北(こうがん きたへかえる)
末候 虹始見(にじ はじめてみえる)
ならわしと生活
4月8日 花まつり・卯月八日

花まつりは灌仏会(かんぶつえ)というお釈迦さまの誕生をお祝いする仏教行事です。
その起源は平安時代まで遡ると言われていて、
「花まつり」という呼び方は明治時代に浄土宗が採用したと言われています。
鮮やかな花々で飾られた花御堂(はなみどう)にいらっしゃるお釈迦さまの像に参拝者が甘茶を駆けます。

これはお釈迦さまが誕生された際、天から神々が降りてきて祝福の為に寒露の水を注いだという経典の説示に由来するそうです。
卯月八日は神さまを山からお迎えしたり、山に入って神さまを里へお連れする行事です。
山からつつじやシャクナゲなどの野花を高い竿の先に括り付けた『天道花(てんとうばな)」を掲げます。
山から採ってきた花を山や田の神さまの依代として飾ることで、
神さまのお力をいただいたり、亡くなった人の供養をします。
これを太陽・月・星の神さまへのお供えとしている地域もあります。
十三参り

旧暦の3月13日頃には数え年で13歳になった子が虚空のように広大な知恵を持つ虚空蔵菩薩さまに知恵を授けていただき、幸せな人生を送ることが出来るように祈願する行事です。

大人の帯を締めて13歳(干支を一周)まで健康に育ったことのお祝いに行きます。
生活
新生活のはじまりもあり、緊張から自律神経や胃腸にトラブルが現れやすいと言われています。
身体を動かす肝木の養生と反対に身体を休める脾土の養生を。
木の氣が上向きに流れすぎて、イライラしたりテンションが上がりすぎている時や逆に滞ったことで不安に駆られたり氣の減退を感じた時は肝木の養生を。
脾土の養生は自分の内外に溜まってしまった毒素を浄化します。
浄化(デトックス)することで、自分のエネルギーのスペースを作ります。

その時その時の状態を見てオン・オフをはっきりとさせるってことだね♪
春の土用入り
清明の終わりには土用入りを迎えます。
土用は次の季節への準備期間でもあり、春の土用は変化や変革のエネルギーを持ちます。
この時期、特にたまった毒(自分に必要のないもの)を浄化して、手放すことで新たな世界を作り上げるための準備を固めていく時期。
土用の期間にエネルギーがきちんと循環できていないと、氣が散漫となりフワフワと足のつかないことが多くなりがちです。

グラウンディングを兼ねて、間日にガーデニングをするのもお勧めです。
ストレスをより感じやすいこの時期、特に土用の期間はお腹に症状が現れやすい時期でもあると言われています。
深い呼吸と添加物の少ない体に優しい食事をいつも以上に意識することが大切であると言われています。

土用と言えば夏の土用の丑の日にウナギを始め「ウ」がつくものをいただく。
というのが有名ですが、春の土用には戌の日に『イ』のつくものをいただくと良いんですって。
この時期は特に季節のエネルギーを感じやすい時期。
春を見つける遊び『春みっけ』は季節のエネルギーを取り入れるお手軽な方法です。
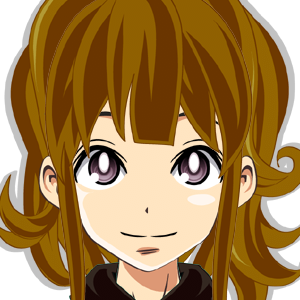
小さい子たちが良くやるやつだよね。
道端のお花を摘んだり。

そうそう。
秋みっけみたいに大量どんぐりお持ち帰りにはならないから良き。